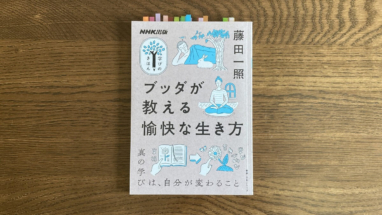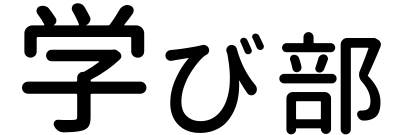先週最終回だったNHKの朝ドラ「おかえりモネ」の感想を、『おかえりモネ メモリアルブック』を読んでまとめます。
というのも、私にとって強烈なインパクトのあるドラマだったので、背景をもっと知ろうとはじめてドラマの関連本を買ってみて、このインパクトの正体はこれだったのか、と気づくことが多かったからです。
この気づきは特に、この本の最後の最後に書かれていた、脚本の安達奈緒子さん、制作統括の吉永証さん、チーフ演出の一木正恵さんの3人の、ドラマに込めた思いの中にありました。
結論からいうと「おかえりモネ」は、「人生の痛みと向き合うって、こういうことなんじゃないか」と教えてくれるドラマでした。
以下、この制作スタッフ3人の印象的な言葉の数々を紹介し、感じたことをまとめます。
\ 〈おかえりモネ〉配信中 /
背景は東日本大震災
まずは、脚本の安達さんのこの言葉から。
東日本大震災を背景に書かねばならないと決まったとき、主人公の百音を不可抗力から“そのときそこにいられなかった人”と設定し、だからこそ“なんとしてでも寄り添いたいと思っている人”としたのは、やはり制作者である私たち自身が“絶対に当事者たりえない”という、痛烈な思いからでした。被災者の方にお話を伺うと、すざまじい経験をされている。それらをいくら自分の身に置き換えてみたところで、どこまでいっても想像の域を出ませんし、その方の本当の苦しみはわからないし、わかろうとすること自体おこがましい。わからないのはどうしようもないことならば、それを前提に、一緒に生きていくにはどうしたらいいのか――。
まず大前提として、おかえりモネのドラマの背景は東日本大震災です。
私のように、日本で多数を占める東日本大震災の当事者でない人が、実際に被災した方と向き合うときにどうしたらいいか。
その帰結として、プロデューサーの吉永さんはこう書いています。
〈おかえりモネ〉は、明るく楽しくテンポよく、というような、いわゆる“朝ドラ”らしい作品ではありません。
朝ドラらしさが「明るく楽しくテンポよく」だとわかった上で、東日本大震災を背景にすると決めたことで、あえておかえりモネの世界観に挑戦したことがわかります。
おかえりモネのネットでの評価に、「暗い」「重い」という言葉が出てきても、それは当然といったところでしょう。
また、ここで言う安達さんの「すざまじい体験」の一部が、新次の「最愛の妻が行方不明で船もなくした」こと、モネの「火事で燃える島を遠くから見た」こと、小学校の先生だった亜哉子さんの「担任だった児童を置いて学校から出ようとした」こと、究極にはみーちゃんの「おばあちゃんを置いて逃げた」こと、だったのですね。
被災の経験の中にも、様々な辛さがあることを教えてもらいました。
被災者の方と一緒に生きていくにはどうしたらいいか
安達さんは答えの一つとして、こう書いています。
その答えの一つを、第16週で菅波が百音に言う「あなたの痛みは僕にはわかりません。でも、わかりたいと思っています」というセリフに込めました。たとえ痛みを共有できなくても、究極的には相手のために何もできなかったとしても、「わかりたいと思っている」と伝え、そばに居続けること。あなたの痛みを、ほんの一瞬でもいいから癒せる存在になれたらという、それは願いというより祈りに近いのかもしれません。
もちろん、それが誰もが納得する答えだとは思いません。それでも、「今の自分が選ぶとしたら、解答はこれだ」というものを探り、物語として紡いでいく作業は、確信はないけれど進むしかない、闇夜を行くようなものでした。
ドラマで一番伝えたかったセリフが、菅波先生の「あなたの痛みは僕にはわかりません。でも、わかりたいと思っています」だったのですね。
そしてこのセリフが、誰もが納得する答えだとも思わない、とも。
確かに、誰もが納得する答えは難しいでしょう。
それでも自分の身に置き換えたとき、身近に辛い経験をした人がいたら、できることはこういうことなのかな、というヒントをもらいました。
立ち止まることにも意志がある
安達さんの言葉でもう一つ印象に残ったのが、次の内容です。
前向きで未来を思考する方に大きな影響を受けた一方で、新次や宇田川さんのように、前を向けない、向かないことを選んだ人々をないがしろにするような物語にはしない、という思いも同じくらい強く持っていました。立ち止まることにも意志がある。亮の、新次に対する「立ち直って船に乗って欲しい」という期待は、深い愛情ではあるけれど、ある種の“暴力”であるとも考えます。
もちろん生きていくからには、良い方向へ向かおうとするのは正しいことです。傷ついても前に進もうとする人間はすばらしい。でも、人が生きることは、どんな形であれ傷を負い続けていくことにほかなりません。追った傷が消えることは決してないし、少なくとも他者が「治さないとだめだ」というのとは違います。「もう痛くないよね、大丈夫だよね」と引っ張り出すようなことは、絶対にしてはいけない。
誰であれ、傷が痛む人には「痛い」と言い続ける自由があるし、その時間は必要なものだと私は思います。
新次の「俺は立ちなおらねぇ」や、行方不明の妻の死亡届に判を押すときの「ひとりで海をゆくのがおにあい」というセリフ。
また、引きこもりの宇田川さんが最後まで引きこもりのままだったこと。
これらは、安達さんの「前を向けない、向かないことを選んだ人々をないがしろにするような物語にはしない」という思いがあってなのですね。
期待が“暴力”になることもあるんだと、考えさせられました。
震災から10年、だから何?
安達さんは、こんなことも書いています。
震災から10年、この物語は、前を向いて進んできた方と、治らない傷を抱えて「10年だから何?」と思っている方――その両方を肯定したいと思って書きました。
チーフ演出の一木さんの言葉はこうです。
この物語をどう終わらせるかは、安達奈緒子さんと共に最後まで悩みましたが、「ドラマくらいハッピーエンドに」といった、勝手な“期待”を込めたラストは選べませんでした。「まだ何も終わっていない」というリアルも、誠実に示したつもりです。
最終回の耕治のセリフ「そんなもんじゃねぇだろ、そんな簡単じゃねぇだろ」は、「10年だから何?」と思っている人の肯定で、「まだ何も終わっていない」というリアルだったのですね。
あらためて、震災に誠実に向き合ったドラマだとわかりました。
おかえりモネが目指したものと、教えてくれたもの
おかえりモネが目指したものを、チーフ演出の一木さんこう書いています。
〈おかえりモネ〉で目指したのは、前を向く人の崇高さだけでなく、取りこぼされがちな、けれど確実に存在する、迷い、立ち止まり、後退し、失敗する、当たり前の人々の姿をも描くことでした。
一木さんのいう、「迷い、立ち止まり、後退し、失敗する、当たり前の人々の姿」。
そして安達さんのいう、「人が生きることは、どんな形であれ傷を負い続けていくことにほかなりません」。
おかえりモネで出てきた、胸をえぐるようなセリフの数々、
「俺は立ちなおらねぇ」
「一人で海を行くのがお似合い」
「お前に何がわかる」
「おばあちゃんを置いて逃げた」
「きれいごと」
に、当たり前な人々の、傷を負った姿を見せつけられました。
あらためて振り返ると、私にとって「おかえりモネ」は、「人生の痛みと向き合うって、こういうことなんじゃないか」と教えてくれるドラマでした。
以上、メモリアルブックを読んで振り返ったおかえりモネの感想のまとめでした。
\ 〈おかえりモネ〉配信中 /