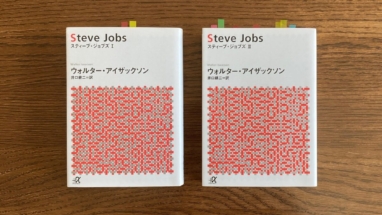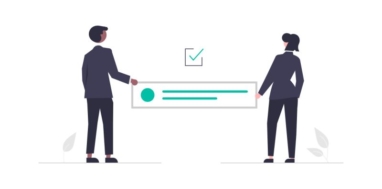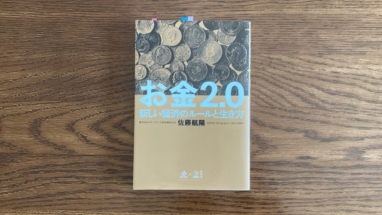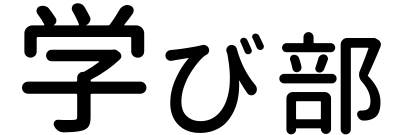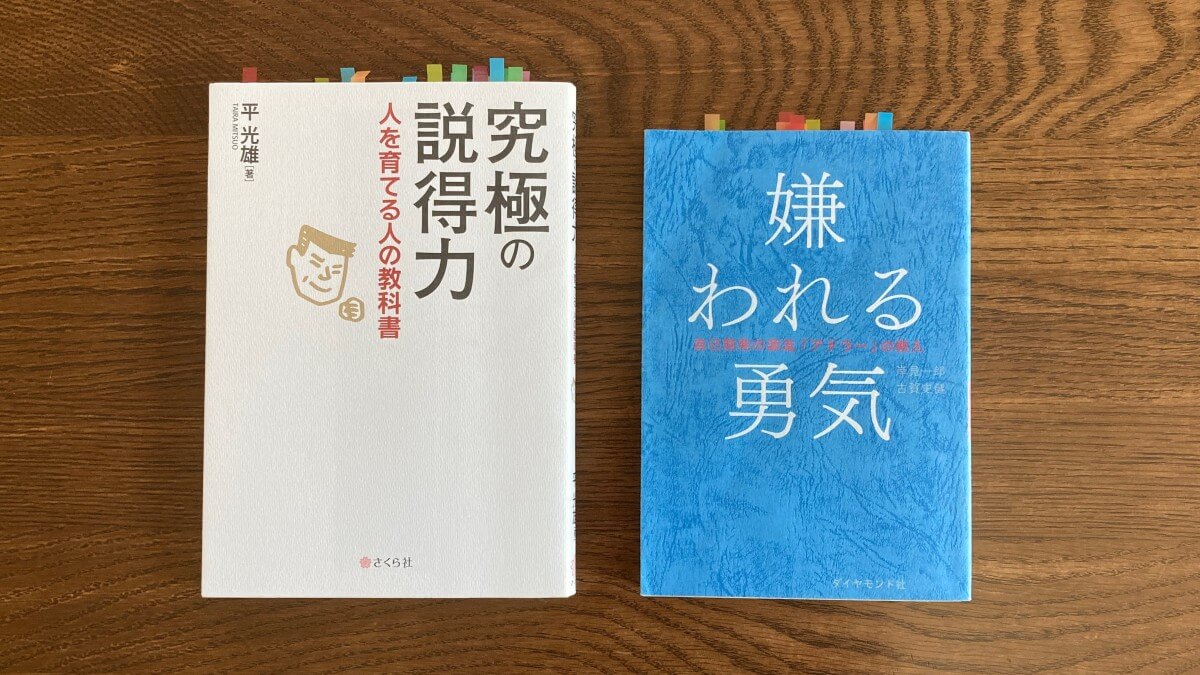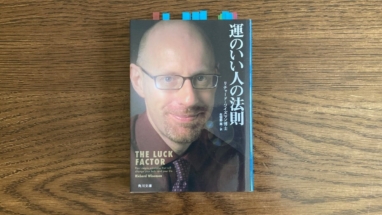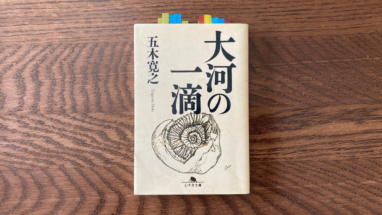もう20年近く前のこと。
当時勤めていた会社にパワハラ気質の部長がいて、課長になった親しい先輩に、「お前、部下に好かれようと思っていないだろうな~」と説いていました。
その意味は、好かれたいと思うようでは部下に仕事をさせることはできない、といったところです。
その部長の仕事のスタイルは高圧的で威圧的なもので、私自身は苦手なタイプでした。
ほどなく私も部下を持つようになり、この部長の言葉がわかるような気がしてきます。
一方で、できれば部下に好かれたい、また好かれた方がチームとしていいんじゃないかという気持ちもあり、結局、ずっと迷ってきました。
この迷いがスッキリするの言葉が、最近読んだ平光雄さんの著書『究極の説得力 ~人を育てる人の教科書~』の中にあり、胸に響きました。
「好かれなければならない。説得力を持つために」
著者の平光雄さんは、30年以上にわたり小学校の学級担任を自ら進んでやってきた教師で、長年の悪戦苦闘からつかんだ「実学」として、この本を書いています。
そして「教師にとって最も大切なものは説得力である」とし、こう言います。
何が最も大切か。
「相手に好かれること」である。拍子抜けしただろうか。しかし、人は好きな人の言うことならきく。相手が嫌いであれば、いくらいいことを言ってもきかない、ききたくない。といえば納得がいくだろうか。それが現実である。実学である。
もちろん、八方美人になれというわけではない(そんなことをすれば、その優柔不断さや抜け目のない利己心が露呈して、ますます嫌われるのは目に見える)。
しかし、人前に立ち人を動かす以上、抵抗のある言葉かもしれないが「好かれる努力」は必須である。
好きではない、ゆえに説得力のない教師に教えられる子どもは不幸になるからだ。
確かに、自分が生徒のときは、好きな先生の授業の方が集中して勉強できました。
働いてからは、好きな上司の元の方がモチベーションが高まりました。
教師であれ上司であれ、説得力が重要なことに変わりはありません。
でも、「好かれなければならない」と、ベストセラーの『嫌われる勇気』の内容が気になります。
タイトルからして「嫌われる勇気」ですから…。
読み返すと、こうあります。
自由とは、他者から嫌われることである。
他者の評価を気にかけず、他者から嫌われることを怖れず、承認されないかもしれないというというコストを支払わないかぎり、自分の生き方を貫くことはできない。
これはこれで、なかなか説得力があります。
この言葉の前後をよく読むと、『嫌われる勇気』が説くのは、「誰からも嫌われたくない」という承認欲求が不自由さを強いることです。
わざわざ嫌われるような生き方をしろ、と言っているのではありません。
考えるに、「誰からも嫌われたくない」と思うと、不自由な生き方になってしまうのでしょう。
人生に「嫌われる勇気」は必要だとしても、平先生の言う「人は好きな人の言うことならきく。相手が嫌いであれば、いくらいいことを言ってもきかない、ききたくない」は、実社会の実学として、覚えておきたい言葉です。
結論としては、
ではないでょうか。
もし今20年前の私が目の前にいたら、こう言います。
堂々と、部下に好かれる努力をせよ!
以上、上司は部下に好かれるべき?という話題でした。