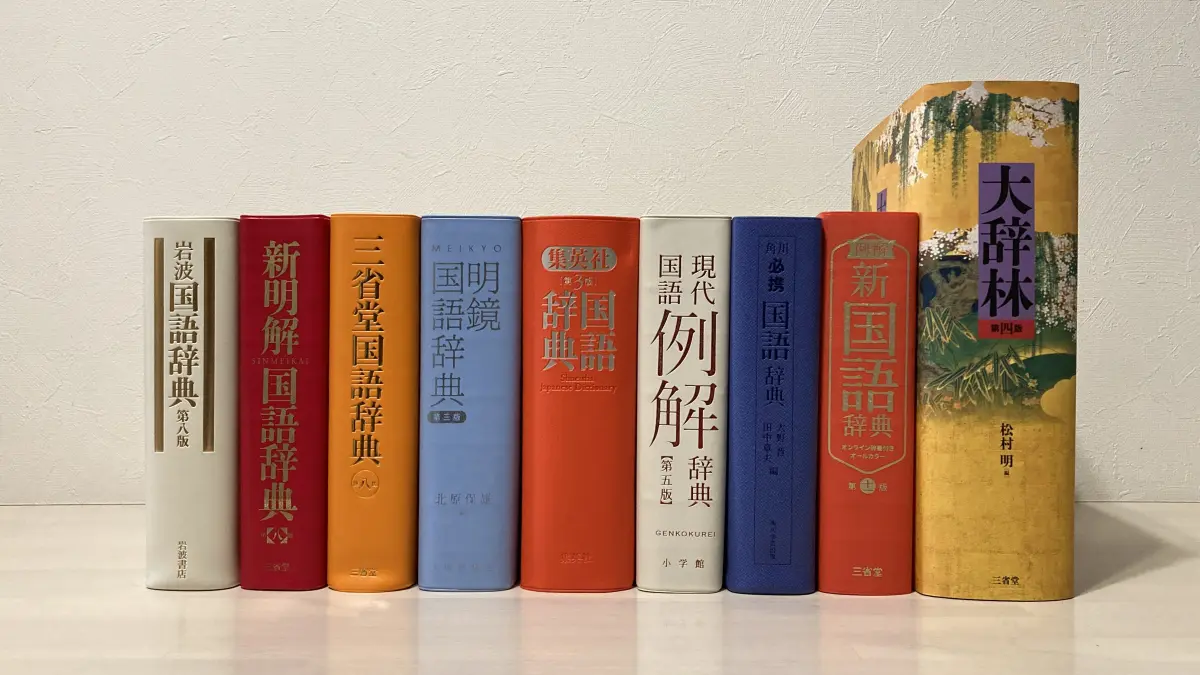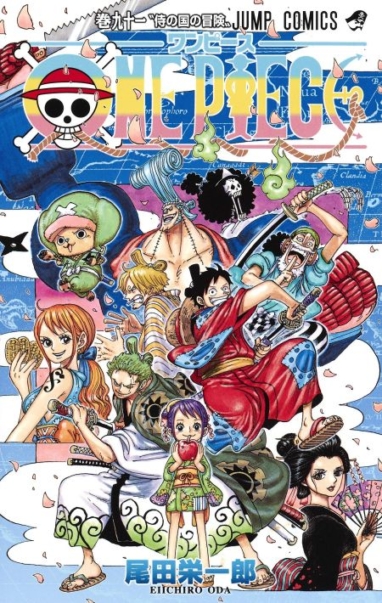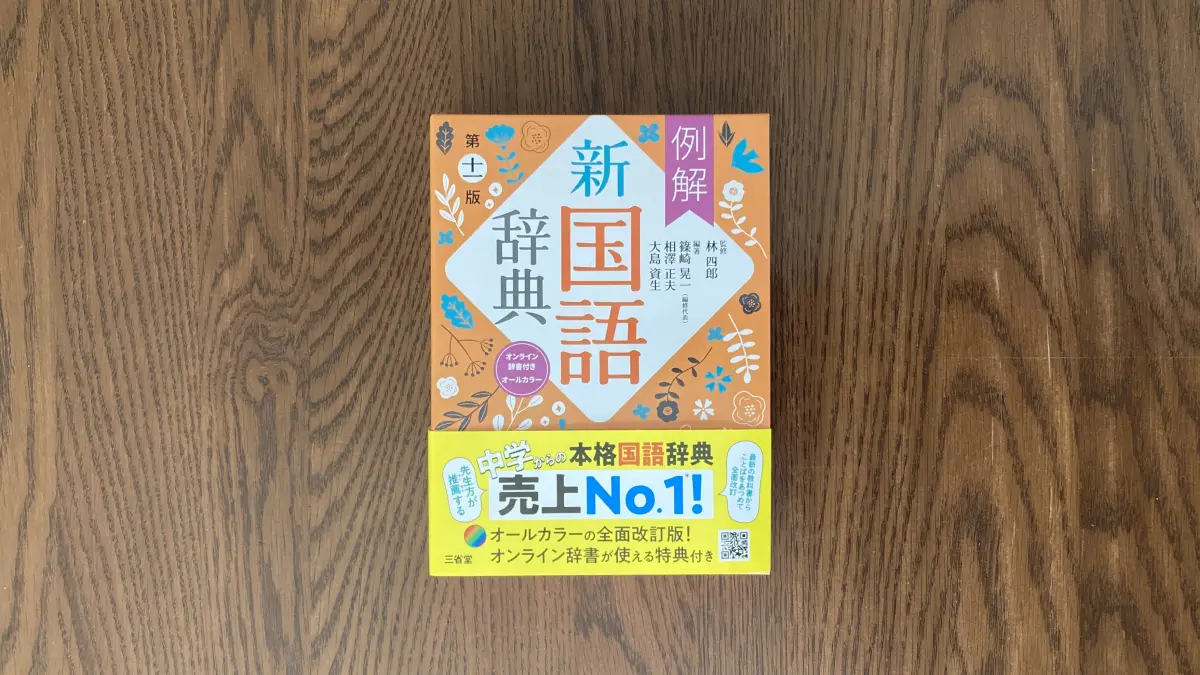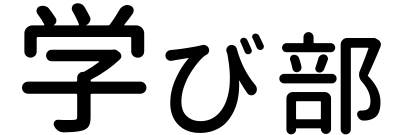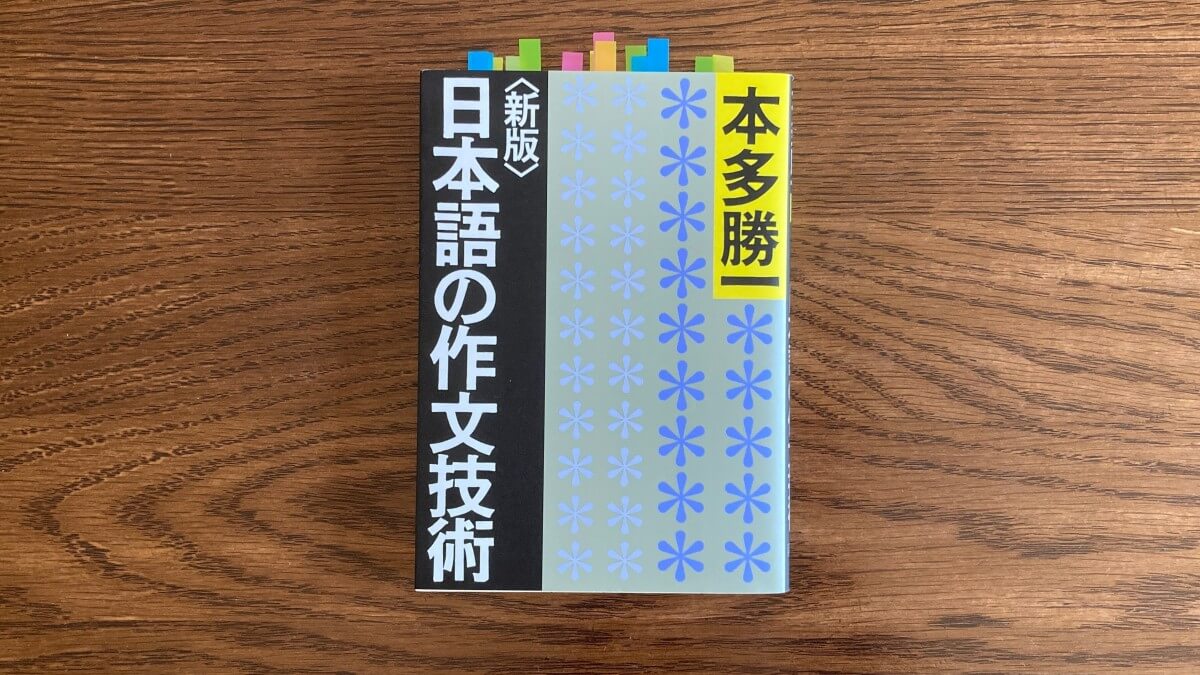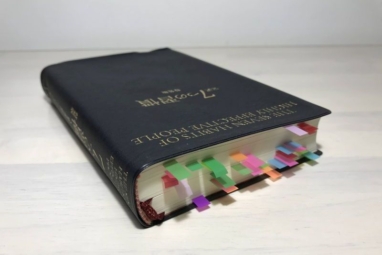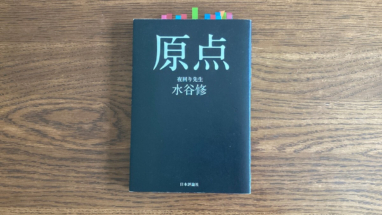書店の棚に「字を大きく読みやすくした新版」になった本多勝一さんの『<新版>日本語の作文技術』を見つけ、買ってみました。
旧版の『日本語の作文技術』は、たぶん10年近く前に買ったのですが、字が小さくて読めずにいた本です。
確かに読みやすく、今度は通読できた!
そしてこの本で初めて、「日本語の主語廃止論(主語否定説)」を知りました。
書中に『言語学入門』(樋口時弘ほか)から、次の引用があります。(p179-180)
主題は存在するが主語は存在しない文も、けっしてまれではない。
日本語について言えば、文の基本的要素は述語であって、主語は目的語・補語などと同じ資格であり、一種の修飾語と考えることができる。
これまで当然のように、「主語」と「述語」があるのが言葉として自然と思っていましたが、間違いのようです。
実は以前に、『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室 (新潮文庫)』を読み、以下の内容になるほどと思いつつも、本当に主語を消していいのか不安でした。
「私」とか「僕」といった自分を指す人称代名詞は、ほとんどの場合、全部、削ったほうがいいんです。日本語は主語を削ると、とてもいい文章になるというのが鉄則ですから。なるべく主語を消していく。
今回、「主語廃止論」を知って、井上ひさしさんの言うことがすんなりわかった気がします。
「主語」についてさらに調べてみようと、ロングセラーの『理科系の作文技術 (中公新書)』を読み返してみたところ、「8 わかりやすく簡潔な表現」の「8.1 文は短く」に、こうあります。
いつでも「その文の中では何が主語か」をはっきり意識して書くことが必要だ。主語を文字に書き表すことはかならずしも必要ではない。しかし、自分がいま書いている文では何が主語なのかはいつも明確に意識していなければならない。
また、『「超」文章法 (中公新書)』には、わかりにくい文章の例として以下が出てきます。
「主述泣き別れシンドローム」
「主述ねじれシンドローム」
「主語述語失踪事件」
私自身の心得として、
が、
と覚えておこうと思います。
以上、本多勝一さんの『<新版>日本語の作文技術』から、日本語の主語廃止論の紹介でした。