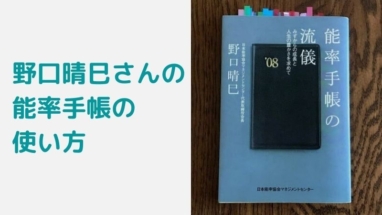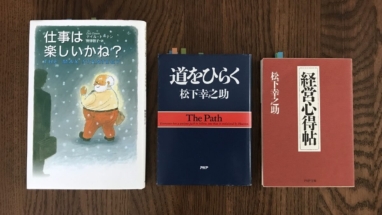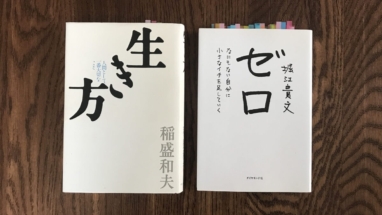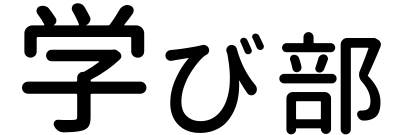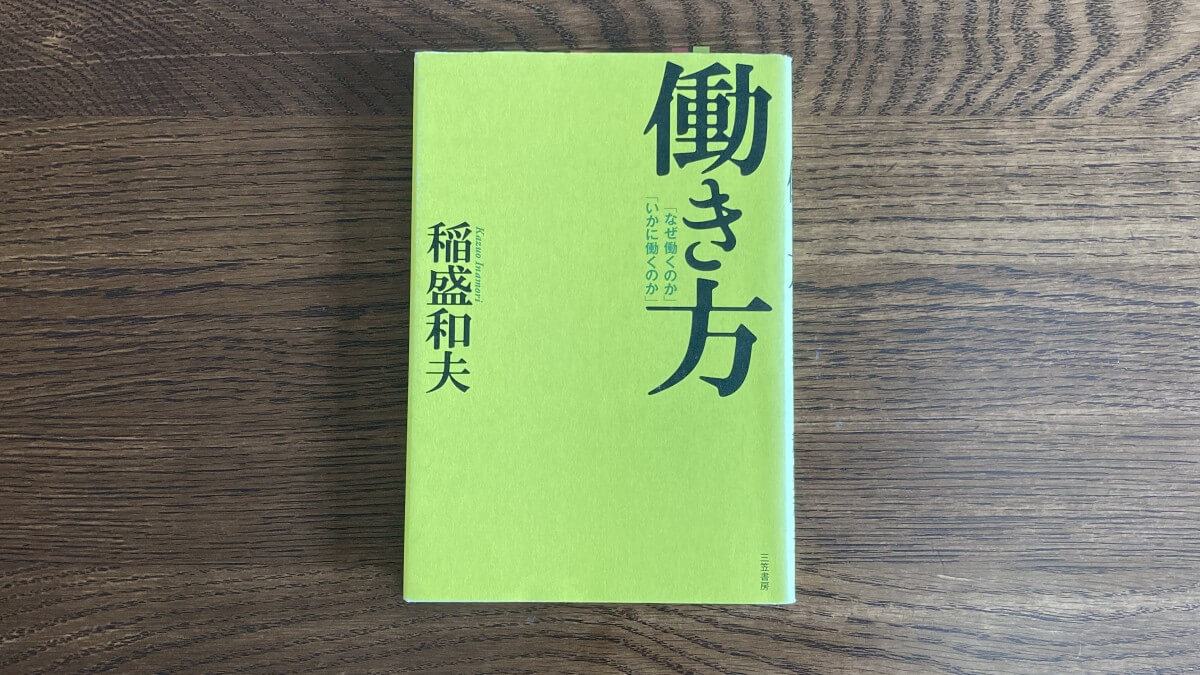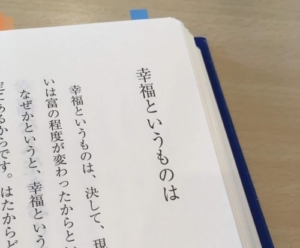稲盛和夫さんは著書の『働き方―「なぜ働くのか」「いかに働くのか」』の中に、「京セラでは長期の経営計画を立てない」と書いています。
京セラという会社は、これまで長期の経営計画を立てないでやってきました。
なぜ、長期計画を立てないか。
それは遠くを見る話というのは、たいていウソに終わるからです。
「何年後には売上をいくらにして、人員はどのようにして、設備投資はこうして・・・・・・」といった青写真をいくら描いても、必ず、予想を超えた環境の変化や、思いもかけない事態が起こります。そして計画変更や下方修正を余儀なくされ、ときには計画そのものを放棄しなくてはいけなくなってしまうのです。
こうして計画変更が続くと、士気や意欲を削ぐ、と言います。
また目標が遠大であるほど途中で萎えたり妥協したりしてしまう、とも言います。
人間の心理的な側面からも、目標に至るプロセスが長すぎる、つまりゴールが遠すぎる目標というのは、往々にして挫折で終わることが多いものなのです。
途中で反故になってしまうような計画なら、はじめから立てないほうがいい。
日本を代表する大企業の京セラが長期計画を立てなかったとは、驚きです。
そういえばヤマト運輸の小倉昌男さんも、著書の『小倉昌男 経営学』で、「ダントツ三カ年計画」という経営計画を3回繰り返し9年間行ったが、いずれもこれで良いというところまで行かなかったことを書いています。
また、元日本能率協会マネジメントセンター(JMAM)会長の野口晴巳さんも、著書の『能率手帳の流儀』に夢や目標についてこんなことを書いています。
- 明確な目標を描き出せるのはごく稀なケース
- 無理やり自分を納得させた目標は、不幸を招く
- あまり大きな目標は挫折につながる
- とてつもなく立派な目標は書かなくていい
- 綿密な計画は立てない
- 遠大な計画は書かない
- できもしないことは書かない
う~む。
私はこれまでビジネス書を読んで、「3~5年先までの計画を立て、年間、月間、週間、一日の計画に落とし込む」とあるのを読むと、なるほどその通りと思ってきました。
代表は、『夢に日付を! ~夢実現の手帳術~』(渡邉美樹)です。
そして2008年に一度、〇〇歳で年収~、〇〇歳で年収~、〇〇歳で年収~、と手帳に書いたことがあります。
そのときは当面は当時勤めていた会社で働き続けるつもりで、この後、まさか1年後に転職を決めるとは思いもしませんでした。
年収目標の結果も未達です。
以後、手帳に〇〇年後に~、〇〇年後に~、という目標を書いたことはありません。
いまはっきりわかったのは、3年後や5年後の計画を立てて実践するという、稲盛和夫さんや小倉昌男さんができないことを、私にできるわけがなかった!
ちょうど新年を迎えるにあたり、これからは「夢や目標を実現するための3~5年の計画を立て、一日に落とし込む」という考え方を、やめることにします。
ではそんな稲盛さんがどうやって、京セラやKDDIを世界的な企業にし、JAL再建ができたのか。
それは、「一年だけの計画を立て、一日だけを懸命に生きた」からです。
くわしくはこちらの記事に書いています。
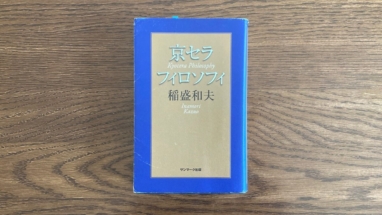
>>>今の京セラには中期経営計画がある?
現在の京セラのIR資料を見ると、2017年度に現社長のもと「2021年3月期 売上2兆円 税引前利益率15%」という経営計画を立てているようです。
これ以前のIR資料には中期経営計画は見当たりません。
⇒ 京セラ 2017年10月31日実施 決算説明会 スピーチ
稲盛さんが経営の第一線を退いているからでしょうか。京セラがこの計画を実現できるか、注目ですね。