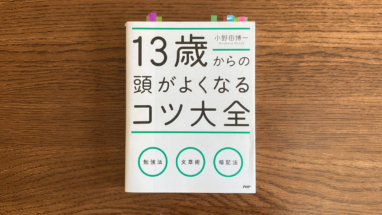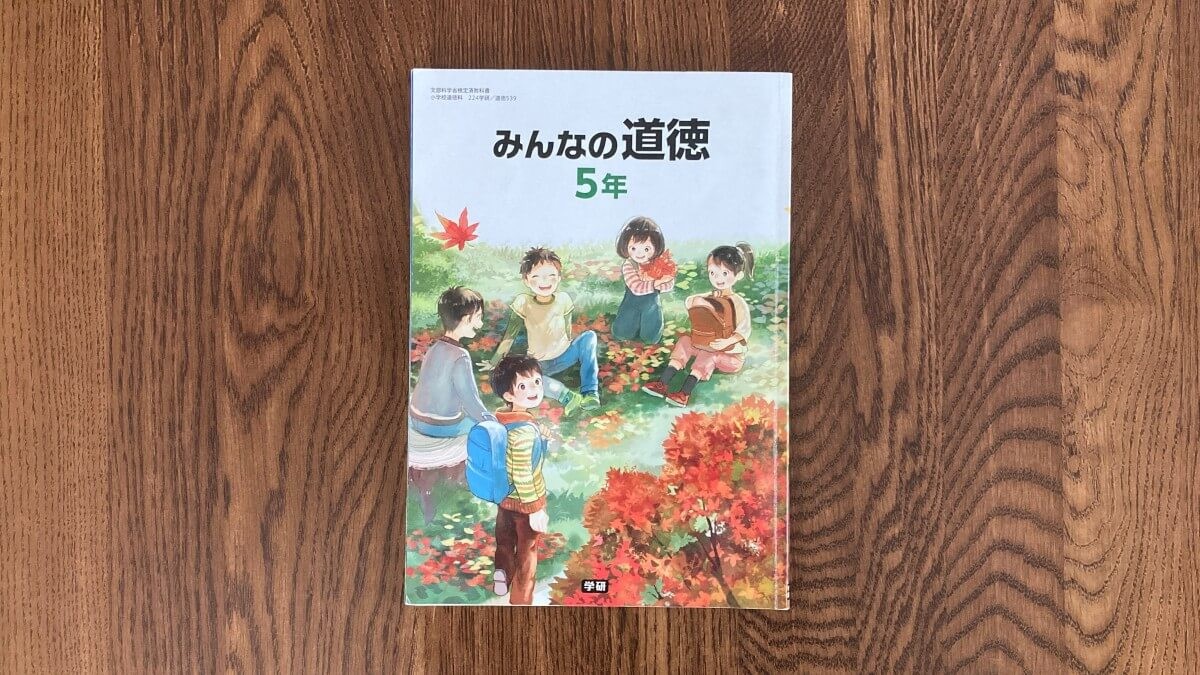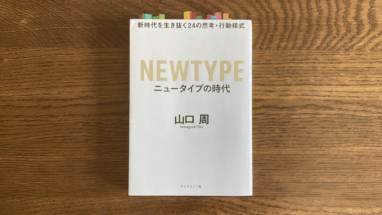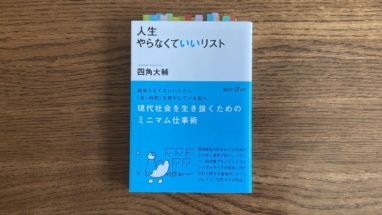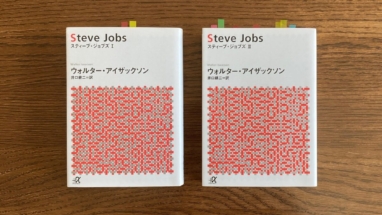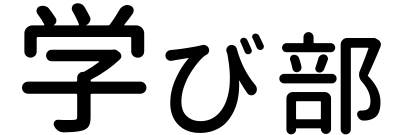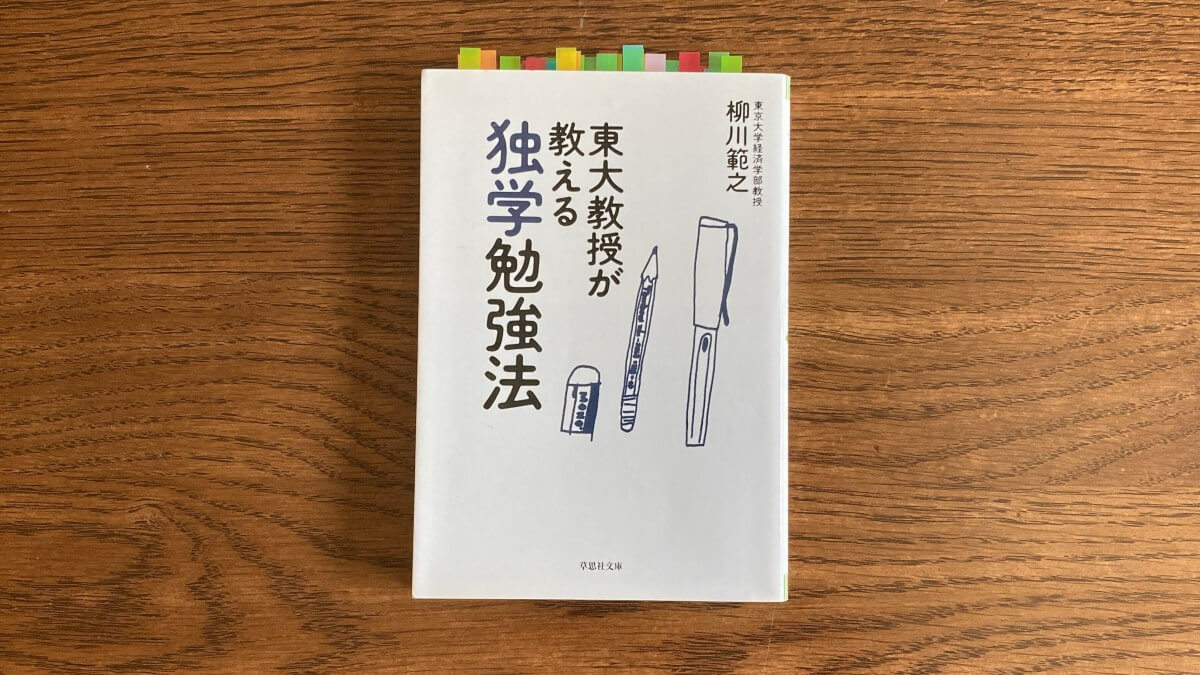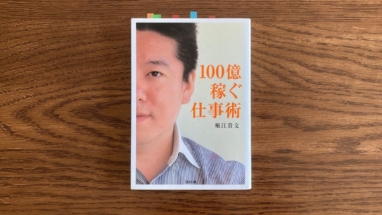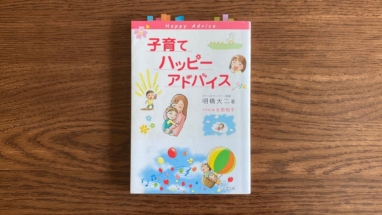こんな疑問を解決したくて、東京大学の柳川範之教授が書いた『東大教授が教える独学勉強法』を読んでみました。
柳川先生は東大の教授といっても、日本の受験エリートではありません。
日本の公立中学を出てから父の転勤でブラジルに渡り、大検を受けて慶応の通信過程に入った後に東大の大学院に進んだ、独学中心の経歴です。
そんな先生の本を読んで、独学うんぬんよりもまず、自分が「勉強の本質」について全然わかっていなかったことを知りました。
正解を見つけるのではなく、答えのない問いに自分なりの答えを見つけるのが、本当の勉強だったとは!
この記事では、この本から学んだ「本質的な勉強」や「独学の方法」について紹介します。
勉強の3つのタイプ
まず柳川教授は勉強を、次の3つのタイプに分けます。
1.明確なゴールがある勉強(受験勉強や資格試験の勉強)
2.教養を身につけるための勉強(趣味的な世界の勉強など)
3.答えのない問いに自分なりの答えを見つける勉強
私のこれまでを振り返ると、まず大学受験に向けて1の「明確なゴールがある勉強」をしてきました。
団塊ジュニアの第二次ベビーブーム世代で、受験戦争がもっとも激しかった時代です。
大学入学後は、普段から何か勉強をすることはなく、試験前だけ単位認定を受けるために、また1の勉強をします。
法学部だったので、勉強自体を司法試験というゴールに合格するためのもの、と思っていました。
本来大学生は卒業論文で、3の「答えのない問いに自分なりの答えを見つける勉強」をするのでしょう。
しかし私のいた大学の法学部は、卒業要件に論文がありません。
ゼミで何か書いたものを提出はしましたが、そもそも論文をどう書くか、考えた記憶すらありません。
社会に出てからも、やる気の出し方や仕事のやり方などの「正解」を見つけるために、本を読んで来たように思います。
大学入試問題の解法テクニックを暗記するような感覚です。
例えば、少し前に読んだ『「ユマニチュード」という革命』という本にいくつがを線が引いてあります。
一ケ所あげると、「ユマニチュードは認知症の人や高齢者に限らず、ケアを必要とするすべての人に向けたコミュニケーションの哲学であり、その哲学を実現させる技法です」というところに青線を引き、「哲学」と「技法」ということばを青でマルしています。
あとで、「ユマニチュードとは何か、次の4つから正しいものを選べ」という試験があるかのようです。
しかし、このことばだけを覚えていても、実社会では全く意味なしです。
「哲学」とはどういう考え方か、「技法」とはどんな技術か、じっくり考え、他人に説明できるくらい理解しているかが、本来は大切なはずです。
世の中のほとんどの正解はわかっていない
結局のところ私は、大学入試の試験のように、世の中のすべてに「正解」があって、どこかの本にその「正解」が書いてあるはず、と考えてきたんだと思います。
しかし、柳川教授はこのようにいいます。
実際には深く勉強していけばいくほど、正解がないというケースがあちこちに出てきます。学者が研究している問題のほとんどは、はっきりした答えというものはありません。
これが、大きな気づきでした。46年も生きてきて!
そしてこういいます。
学問に限らず、世の中のほとんどのことについて、何か正解なのかよくわかっていないのです。だから、仕事においても、生活においても、本当に重要なのは、正解のない問題にぶつかったときに、自分なりに答えを出そうとして考えていくことだと思うのです。
なるほど~。
いまの私の場合でいうと次の問いに、明らかな、確実な、はっきりした「正解」はないのだと。
- 会社の収益を増やすにはどうするか
- 自分の給料を上げるにはどうするか
- 今の仕事をこのまま続けていくか
- 息子をどう育てるか
- 奥様は、どうしたら機嫌よくいてくれるのか
- 究極は、どうしたらしあわせになれるか、しあわせとは何か
しあわせについての「正解」は、少し前は、「偏差値の高い大学を卒業し、大企業に入るか公務員になるか、医者か弁護士か会計士になって、結婚して子どもをつくり、家と車を買って、引退して退職金や年金で悠々と暮らす」、だったかもしれません。
今では、幻想ですよね。
自分なりの答えを選び決めるための独学法
この本ではこう説きます。
これらの問いには、自分で深く考えて、自分なりの答えを「選ぶ」「決める」必要がある。そのために有効なのが独学だ。
そして、勉強する前に、勉強する姿勢としてこう言います。
本の内容を覚える必要なんてまったくない。
まずは、何でも疑ってかかるクセをつけてみる。
つねに「自分がどう思うか、どう考えるか」を考えるクセをつけよ。
そのうえで、具体的な勉強のやり方や本の読み方のを教えてくれます。
- 最初から情報や資料を集めすぎない
- まずは入門書を3冊買う
- 本の中に正解を探さない
- あくまで読者が自分で考えていくための材料でしかない
- 2段ステップで読む(最初はそのまま受け入れる、次は批判的に)
- 1回目はいきなり線を引かない
- 大事なポイントと思っても、初めて読んだからにすぎないからかも
- 線を引くより繰り返し読む
- ノートをつくらない
- 要約しない
熟成というプロセス
また、学ぶことにおいて一番大事だと著書が強調していることが、「熟成」というプロセスです。
勉強とは加工業のようなものではないかと思います。(中略)その加工をする際、大切なのは、自分の中で「熟成させる」という工程です。ここで「熟成させる」というのは、自分の中でしっかりその情報を吟味して、その意味を考え、自分のものにする作業です。
即席生産、促成栽培の時代だからこそ、得られた知識や情報を自分の中でどう加工するかをじっくり熟成させ、自分なりのオリジナルな考えや発想を生み出していくことが大事になってくるのです。
ここは、スピードだけを求めても、自分の言葉でアウトプットできなけれは意味はない、と理解しています。
一番、難しいですね。
独学はマラソン
出てくる比喩もうまいです。
いくつか紹介します。
いわば、独学は長距離走やマラソンのようなものです。いきなり最初から全力で走ったら、すぐにバテてしまいます。長い時間を走り通すには、しっかりした準備運動や助走期間が必要なのです。
これは例えばゴルフの練習で、むやみやたらと何百球、何千球と打っているようなものです。それよりも、「何かコツがあるはずだから、そのコツがどうやったらつかめるんだろう」ということを少し考えながら打てば、結果は違ってくるはずです。
例えてみれば、ジョギングをはじめる前に、まずウエアや高級なシューズを買い揃えるという人と同じパターンでしょう。(中略)最初から完璧に用具を揃えようとすると、それだけで疲れてしまったり無駄な労力やコストがかかってしまいます。”
忘れずにいたい言葉です。
まとめ
この本の背表紙では、本の内容をこう説明しています。
「自分で目標を見つけ、問いを立て、集めた情報や知識を自分の中に落とし込みながら考えを深め、それを現実に応用していく」という勉強の全工程について、具体的なやり方を体系的にまとめたもの
その通り!という実感です。
私にとって 『東大教授が教える独学勉強法』 は、「学び」と同時に「希望」の書です。
40代後半の中年でも、やりたいことがあればこれから「独学」して、「自分で考える」ことをしていけばいい、ということです!!!
以上、『東大教授が教える独学勉強法』からの学びの紹介でした。