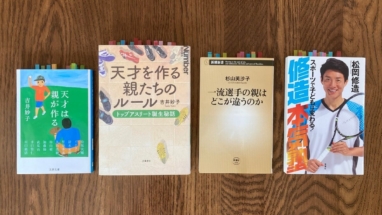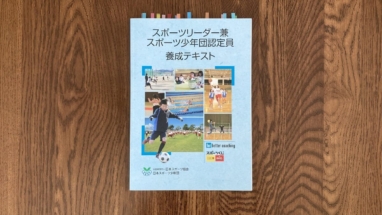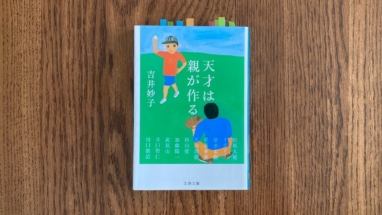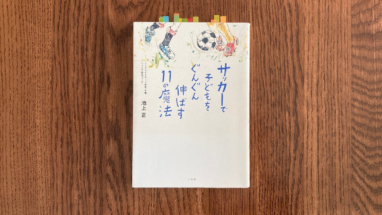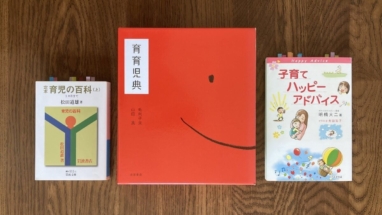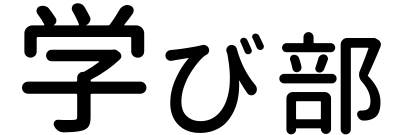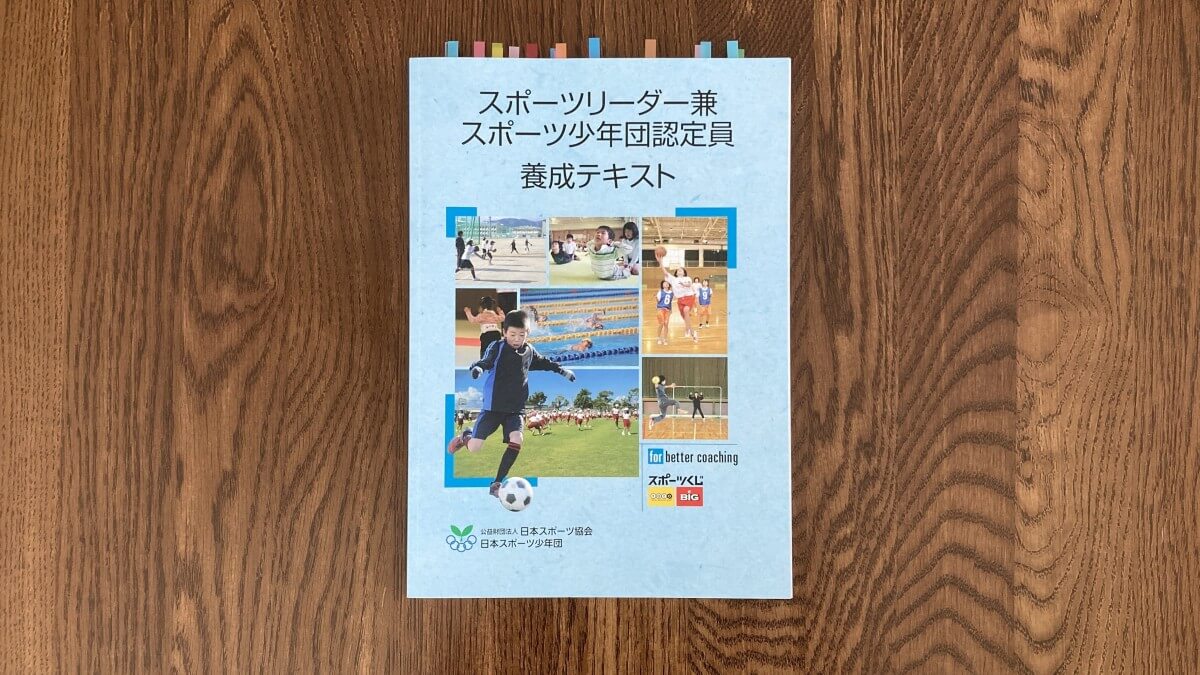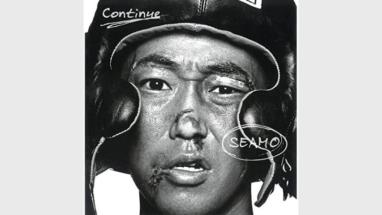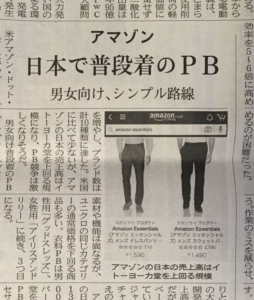この土日に、「スポーツリーダー養成講習会兼スポーツ少年団認定員養成講習会」を受講しました。
朝から夕方まで丸2日間という長丁場の日程です。市の全団体の未取得の希望者が対象で、どれくらい受講者がいるかと思ったら、なんと約60名もいて驚きました。みなさんとても熱心ですね。
この2日間の講義で、今後のスポーツ少年団での活動や、自分自身の子育てに活かしたいポイントがいくつもありましたので、学びや感想をまとめておきます。
(※受講の最後に行われる試験のポイントではなく、個人的な学びのまとめです)
スポーツ少年団の理念とその意義
理念の一つは「スポーツを通じて”からだ”と”こころ”の成長を育むこと」。子どもの成長のための団体。
意義の一つは「自主・自立的な活動」。やりたい子どもたちがやりたいスポーツをする団体。親が無理に押しつけるようなものではない。
これからは団員が中・高校生になっても継続することができる環境の整備が重要。
スポーツ少年団の組織と運営
団員登録は3歳以上(小学生以上と思っていました)。
団員は活動に参加する権利を持ち、規則を守り運営を分担する義務を負う(メンバーシップ制という)。
競技以外の交流活動(野外活動やレクリエーション活動など)も、子どもたちの社会をより豊かなものにし、団の活動をより充実したものにする。
指導者の役割
指導者とは、「スポーツを安全に、正しく、楽しく」指導し、「スポーツの本質的な楽しさ、素晴らしさ」を伝えることができる者。
「スポーツの楽しさ」を自らの態度や実践で表現できるモデルとなり、さらに言動で見本を示す必要がある。
たとえプレーヤーを励ましたり動機づけるための声かけであっても、指導者は一般社会で受け入れられるような言葉遣いをするよう心がけるべきである。
主体はプレーヤー。「Players First」。
「結果管理」より「経過管理」。
「Try & Error」。「失敗する権利」を奪わない。。
プレーヤーがやったことに対して怒ったり、文句を言うのではなく、良いところを見つけて褒める。そうすればプレーヤーは楽しみをおぼえ、次に「どうしたらもっと良いプレーができるのか」を自分自身で考えてプレーしはじめる。ミスを責めるかわりにプレーヤー自身に修正するチャンスを与えることが大切。
プレーヤーが自ら取り組み、工夫し、それぞれの個性が発揮できるような環境を一緒に作る。
文化としてのスポーツ
生涯スポーツ論:ライフステージ毎のQOL(Quality of Life)を高める、生涯にわたって自己開発を求める運動。
スポーツマンシップとフェアプレー:対戦する相手は敵ではなく、自分の可能性を引き出し、高め、競技を価値あるものにする「パートナー」。
「グッド・ルーザー(good loser)」:スポーツにかかわることは、常に負けを味わうこと。したがって負けをどう捉えるかが大切であり、負けたときの態度こそが問題になる。
トレーニング論
ウォーミングアップは一般的には3~5分前後の軽いジョギング→ストレッチ→軽いスタートダッシュ、ジャンプ、ターンなど全身的な運動の流れで、15分前後あれば十分。日本のウォーミングアップは長くなりがち。
スポーツ指導者に必要な医学的知識
傷は、まず水道水で流しながら砂や土などを異物を洗い流したり、傷に食い込んでいる場合はガーゼなどで少しこすって、汚れを取り除く。
スポーツと栄養
水分摂取のタイミングは、運動前から十分に水分補給をし、運動中には喉が渇いたという口渇感が起こってから水分を補給するのではなく、定期的に水分を補給しなくてはいけない。温度は5~10℃が望ましい。
ジュニア期のスポーツ
自分はやればできるという「運動有能感」を持つと、運動好きになるとともに、行動面でも高い積極性や協調性を示すようになる。
「運動無力感」を持つと、運動嫌いになるだけでなく、劣等感が強く、何事にも今日曲的になってします。
胸に刻みたい「グッド・ルーザー」ということば
今回の講義で特にぐっときたことばは、「グッド・ルーザー(good loser)」です。
これはスポーツに限りません。例えば、受験や就職ですべて第一希望の望みをかなえきた人はごく少数でしょう。その意味では大多数が敗者です。社会に出てからも、サラリーマンなら成績や出世で競争にさらされ、いつも勝つことはないはずです。成功している起業家も、いくつもの失敗を経験して今がある方がほとんどでしょう。
よく言われるように、人生では負けることの方が圧倒的に多い。
負けず嫌いの子の中には、試合に負けて泣くならまだしも、負けそうになるだけで泣いてしまい実力を発揮できない子がいます。
そんな子どもたちと、「グッド・ルーザー」の意味をともに学んでいきたいですね。
このことばに出会えていろいろ考えられただけで、2日間の価値がありました。
生涯スポーツを楽しみ、脳を鍛えたい
脳を鍛えるには運動しかないと、最近特に実感するようになりました。
この本のタイトル通りです。
京都大学の哲学者である西田幾多郎先生が哲学の道を散策したり、作家の村上春樹さんがランナーだったり、Testorsteroneさんが筋トレをすすめたりと、精神科医の樺沢紫苑先生が毎度ツイッターで発信したり、参考になる事例はいくつもあります。
運動すると、集中力が高まる!
記憶力が高まる!健康な人も、メンタル疾患の方も同じです。
だから、運動してほしいのです。【YouTubeライブ・樺チャンネル】https://t.co/drFMfvMlRQ#うつ病#メンタル疾患#樺チャンネル#YouTubeライブ #裏しおんちゃん先生@urazionchan
— 精神科医・樺沢紫苑@インプット大全&アウトプット大全 シリーズ64万部突破 (@kabasawa) 2020年1月15日
生涯にわたりスポーツを楽しむことができれば、筋トレよりも効果的だと思います。
試験について
最後にテストがあります。 試験時間は60分。4択からの選択問題が全部で50問で30問以上正解で合格です。
テキスト持ち込み可なので甘く見ていたら、時間の余裕が全くなく、ほぼ時間ギリギリになってしまいました。
講義で講師が伝えるポイントをその場でしっかり覚えるようにすると、時間に余裕ができて楽になると思います。
試験後すぐに採点があり、受講者全員が無事に合格できました。よかった。
最後に、地域スポーツを支えてきた先輩方に感謝
今回の講習に参加した受講者だけでなく、講師や運営に携わる方々のほとんどがボランティアだと思います。
何十年もボランティアで地域のスポーツを支えてきてくださった方々のおかげで、子どもたちが身近にスポーツを楽しめています。
そんな先輩方に、心から感謝をいたします。